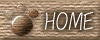学部ゼミ概要
経営学ほど,実践に勝る理論はありません。実際,優れた経営者たちは,実践から独自の理論(持論)を作り上げてきました。犬塚ゼミ2.0では,この経営者の“持論”を読み解くための企業ケース分析(名付けて,ケースマラソン)を行います。退屈な輪読はない代わりに,対象企業もしくは業界を調べあげる準備作業が毎回必須となります。
3年次前半は,グループワークを通して,ケース分析の基礎的な方法論を会得します。3年次後半ではそうした技法を応用し,特定の企業行動について個別に分析していきます。4年次では分析をさらに深め,卒業論文としてまとめあげます。これらの活動を通じて,当ゼミでは2年間でおよそ100のケースを経験します。多くのケース(パターン)を積むことで,変化の予兆をいち早く捉える能力が身に付くと同時に,社会を理知的に生き抜くための知恵が養われます(就活に活かしてください)。
他と差を作ることは,戦略の基本です。当ゼミでは,大学院進学や起業,留学等,他人とは違った“戦略的な人生”を体現したい学生を,積極的に応援します。
学部ゼミ説明会の資料
過去のゼミ活動動画(拡大ゼミ)
入ゼミを考えている学部2年生へ(担当教員からのメッセージ)
いま学んでいることが,将来どんな力になるのか――
正直,実感がわかない人も多いと思います。私自身,学生の頃はそうでした。
私は,ソニーで技術者として働いていました。当時のソニーは理系の就職先として人気ナンバーワンの企業で,内定が決まったときには,さほど親しくなかった人たちからも「おめでとう(大成功だね)」と声をかけられたのを覚えています。
しかしそのソニーは,1990年代後半から約20年にわたり,長い冬の時代を経験することになりました。売上は好調なのに,利益がまったく出ないのです。これはソニーに限った話ではありませんでした。ライバルのパナソニックも業績を悪化させ,シャープ,三洋電機,日本ビクターといった名だたる日本企業が次々と市場から姿を消していきました。日立はテレビ事業などの不採算部門から撤退を始め,東芝は経営を安定化させるために,営業利益の大半を稼いでいた半導体メモリ事業の売却に追い込まれました。まさに,”日本総崩れ”といった状況でした。そうして生まれた空白を,韓国や台湾,中国などの企業があっという間に埋めていったのです。
――自分たちではどうすることもできない巨大な波にのまれている――
私は寒気を覚えました。これからの社会で生き残るには,技術ばかりを追いかけていてはダメだ。大きな波の到来を予測し,それにどう対処するかを考えることの方が,はるかに重要ではないか。そうした力を身につけたい。それが(もちろん,それだけではありませんが),私が経営学を志した理由です。
思えば私は,就職活動(当時は「就活」という略語はありませんでした)の際,「有名な会社だから」「みんなが良いと言っているから」「転勤が少なそうだから」といった,あいまいな理由で就職先を選んでいました。理系出身の私は,経営に関する教育をほとんど受けておらず(受けていたのかもしれませんが,内容を覚えておらず),企業や戦略の良否を判断するための知識を何ひとつ持っていなかったのです。いわば「武器ゼロ」の状態で,巨大な社会の波に挑んでいったわけです。これでは,社会に負けるなという方が無理な話でしょう。
大学教員になった今,私は残念ながら,本学部の学生に,当時の自分を重ねて見てしまうことがあります。せっかく経営や経済を専門として選び,その分野の第一人者(教員)から直接学べる機会があるというのに,その価値を実感できずにいる。いやむしろ,学ぶことを一種の必要悪と捉えている学生すらいるように感じます。一所懸命にやるのはカッコ悪い。自分は余裕だというところを見せておきたい。やがて,「楽勝」「タイパ」といった基準で授業やゼミを選び始め,本来身につくはずの「武器」が身につかないまま,就職活動を迎えてしまう。それはまるで,あの頃の私です。
――経営学を,もっと人生に役立ててもらいたい――
企業の外部にいるわれわれにとって,企業活動を知る手がかりは限られています。しかし,企業は社会との相互作用の中で成り立っている以上,必ずその活動の痕跡を残しています。そうした痕跡(事実)を拾い集めて分析する力を養うことで,「企業がなぜ成功(あるいは失敗)し,それはどの程度続くのか」「与えられた環境の中で,最適な選択(戦略)は何か」「なぜ,正しいとわかっていた戦略を実行できなかったのか」といった経営者の判断を疑似的に体感できるようになります。こうした経営判断の筋(良否)を読み解く力こそが,私が就職前に学ぶべきだった「武器」だと考え,今の形でのゼミを始めました。
「楽勝」や「タイパ」を探し続けることも,社会と対峙するための一つの戦術ではあるでしょう。しかしそれは,水鉄砲で社会に挑むようなものです。いずれ,オモチャは通用しなくなる。社会の中で長く活躍するためには,本物の知識を自分の中に積み上げていくしかないのです。そういう知識は,理論を学ぶだけでは決して身につきません。このゼミでは,実際の企業事例を通じて,経営を「現実の問題」として考える力を磨いていきます。自分の頭で考え,議論し,答えを見つける過程の中で,「知識が人生の武器になる」瞬間を,きっと感じられるはずです。
社会を生き抜くための本物の知識を身につけたい。自分の意思で未来を切り拓きたい――そんな学生の志望を歓迎します。
よくある質問(Q&A)
- Q1. 先生は怖いですか?
A. たまに怖いと言われることがあるのですが,それはおそらく,私が本気で向き合っている姿に接したからだと思います。私は,中途半端な理解で終わらせることが嫌いです。議論の中で厳しく問い返すことはありますが,それは思考の精度を高めたいのと,何より私自身が正しい答えを見つけたいからです。学ぶことに関しては,おそらく私の方が学生よりも貪欲です。それを怖いと感じるかどうかは,ゼミ生に直接確かめてみてください。
- Q2. ゼミの雰囲気はどんな感じですか?
A. 真剣な議論と和やかな雑談が両立する,メリハリのあるゼミです。
- Q3. 授業時間外の活動は多いですか?
A. 基本は授業時間内(金曜日の15時〜)です。ただし,ケース発表のまとめや自主的活動(ビジネスプラン・コンテストへの参加など)では,グループで集まることがあります。他の授業の負担とのバランスには配慮しています。
- Q4. どんなことを学ぶゼミですか?
A. 実在する企業の業績が「なぜライバルと比べて高い(あるいは低い)のか」「なぜA社は回復できて,B社はできなかったのか」等の問いを,自ら情報を集めて分析して発表し,最後はゼミ全体で一緒に考えていきます(その場で一緒に調べることもあります)。理論よりも現場に即した判断力と,仮説を立て検証する思考法を重視します。
- Q5. なぜ,数多くのケースを経験するのですか?
A. 本ゼミでは,他の学生の発表も含め,2年間で約100の企業ケースを扱います。産業や企業がうまくいかなくなるプロセスには,一定のパターンがあり,それは多くの事例に触れることでしか見えてきません。語学と同じで,何度も繰り返すことによってしか身に付かないのです。このケースメソッドは,世界の一流ビジネススクールでも広く用いられている手法で,たとえばハーバード大では2年間で約500件のケースを扱うそうです(余談ですが,ケースメソッドで教える先生には高いスキルが要求されるため,授業料はびっくりするくらい高額になります)。本ゼミで扱う内容は,それを本学の学部生でも無理なく体験できるようにアレンジしたものです。
- Q6. 分析する企業や業界は自分で選べますか?
A. はい。各自が関心を持つ企業や業界を自由に選んで構いません。将来就職したい業界や,ニュースで気になった企業など,自分の関心をもとにケースを設定できます。興味を持って調べることが,学びを深めるための一番の近道です。
- Q7. 経営学が苦手でも大丈夫ですか?
A. もっている知識の量を競うゼミではなく,知識を使って考えるゼミです。苦手意識がある人ほど,ケースを通じて経営の面白さが見えてくるはずです。
- Q8. グループワークや発表は多いですか?
A. はい。というか,ほとんどそれが全てです。ディスカッションやチームでのケース発表を通じて,論理的に考えを組み立て,表現する力を養います。発表は,形式よりも実務的な説得力を重視します。
- Q9. 選考方法はどうなっていますか?
A. 応募書類(志望理由)と面接で選考します。ゼミ選びは,自分選びであり,会社選びと同じです。当ゼミでは,実際の企業採用に近い形式(エントリーシート→グループディスカッション→個人面接)で,書類では見えない自分の魅力をアピールする機会を多く用意しています。
- Q10. 成績は重視されますか?
A. 参考にはしますが,最も重視するのは学びに対する姿勢と適性です。意欲があれば,成績に自信がない人でも歓迎します。
- Q11. 集団面接(グループディスカッション)では何をするのですか?
A. 与えられた課題をもとに,グループで議論して答えを探します(応募人数にもよりますが,1グループ5〜6人です)。当ゼミでは,議論がほぼすべてですので,議論にきちんと参加できるかを確認するのが主目的です。
- Q12. 個人面接ではどんなことを聞かれますか?
A. 志望動機,印象に残った授業,最近関心を持った企業やニュースなどを伺います。正解はありませんので,自分の言葉で話してください。「いい感じのこと」を言おうとするよりも,自分が何にモヤモヤし,何にワクワクするのかを,素直に言葉にする方がよほど伝わります。
- Q13. どんな学生が向いていますか?
A. 経営を概念的にではなく,現実の問題として理解したい人,議論や批判を恐れない人です。完璧でなくても,考えることを楽しめる人を歓迎します。
- Q14. ゼミに入ると忙しくなりますか?
A. 楽ではないものの,努力した分だけ確実に力がつきます。グループでは作業を分担できますし,個人で担当する場合も,発表の頻度は3週間に1回程度です。時間管理は必要にはなりますが,先輩の多くはむしろ楽しんで取り組んでいるようです。
- Q15. 就職活動に役立ちますか?
A. 実在する企業や業界を調べるゼミですから,就職活動に役立たないはずがありません。企業を分析する力,仮説を検証する力,自分の考えを言語化する力を身に付け,多くの卒業生が希望する進路へと進んでいます。また,「100の企業ケースを経験する」という学びは他大学ではまず得られないため,さまざまな面接場面でも大いにアピールできます(実際,インターンや就活面接では,ゼミに関する質問を多く受けるようです)。
- Q16. 就職ではなく,大学院進学や留学を考えているのですが,ゼミ採用には不利ですか?
A. いいえ。むしろ,他人と違う「戦略的な人生」を体現したい学生を積極的に応援したいと思っています(私自身も,他人と違う人生を歩んできましたので)。
- Q17. 倍率は高いですか?
A. 年度によって大きく変わります。応募が多かった年もありますし,逆に定員に満たなかった年もあります。ゼミの人気は,その年の学生の興味関心や,2年次までの授業経験の有無(これは本当に大きい。親近効果ですね),あるいは不確かな噂や憶測など,さまざまな要因によって左右されます。株価と同じで,「去年はああだったから,今年はこうなる」と予測しても,だいたい当たりません。私なら,「本当に学びたいことは何か」「落ちても後悔しないか」を基準に選ぶだろうと思います。
- Q18. 他のゼミと迷っています。どうすればいいですか?
A. 「今の自分には難しくても,一番成長できそうなゼミ」を選ぶことをお勧めします(残念ながら,成長と楽は両立しません)。もしそれが当ゼミでないなら,迷わずそちらへ行ってください。就職先も,「残業が少ない仕事」よりは,「残業をしてでもやりたい仕事」を選んだ方が,人生はきっと充実するでしょう。その意味でゼミ選びとは,社会との付き合い方を考える「自分選び」の第一歩だと思います。
- Q19. 付いていけるか不安なのですが,応募していいですか?
A. ゼミは,最初からできる人が来る場所ではありません。むしろ,悩んだり,迷ったりしながら,少しずつできるようになっていく場所です。わからないことや不安なことがあれば,その都度相談しながら一緒に進めていきますので,心配しすぎなくて大丈夫です。
- Q20. 最後に,何かメッセージはありますか?
A. ほとんどの学生さんはこれまで,「みんなと同じ」「目立たない」ことを無意識に選んで生活してきたのではないかと思います。しかし,社会に出て評価されることはその逆で,問われるのは「あなたは他と何が違うのか?」です。その問いに答えるためには,今のうちに自分だけの経験や視点を増やしておく必要があります。「バイトを頑張った」「サークルでみんなをまとめた」等のありふれたガクチカは,「特になし(私は周囲に流されているだけ)」と言っているようなものです。
人と違う道を選ぶには,強い論理や信念が要ります。企業戦略も同じで,明確な差をつくれる会社には,それが業績につながるはずだという論理(持論)があります。このゼミも,私の信念(持論)のもとに,他の教員ではできない独自性を打ち出しています。100の企業がもつ持論を糧に,みなさんも自分にしかできない「圧倒的な差」をつくり,人生を有利に進めていっていただきたいと願っています。※毎年,11月にゼミ見学(オープンゼミ)の機会を設けています。現役ゼミ生からの”生の声”を聞くことができる貴重な機会ですので,ぜひ参加してください。噂や評判に振り回されず,常に自分の目で確かめて判断すること――それが,当ゼミに入ってから強く求められる姿勢です。
過去のゼミ生情報
- ■主な就職先(*複数名輩出)
(あ)愛知県信用農業協同組合連合会,アサヒ飲料,アビームコンサルティング,アチーブメント,アド近鉄,エステー,大垣共立銀行,オークマ,小田急不動産
(か)鹿島建設,川崎重工業,関西電力,キッコーマン,グリー,コーエーテクモホールディングス,これから
(さ)四国電力,新東工業,ジェネレーションパス,セイフラインズ,ソニー生命保険
(た)中部電力*,中日新聞社,電通九州,デンソー*,電通名鉄コミュニケーションズ,東海東京証券,東海旅客鉄道*,東京海上日動火災保険*,東邦ガス*,トヨタ自動車,豊田通商*
(な)ナガセ,名古屋市役所*,名古屋鉄道*,ニトリ,西日本電信電話*,日本ガイシ
(は)阪急阪神不動産,日立物流,百五銀行,富士フイルム,富士紡ホールディングス,パーソルキャリア,パナソニック,ベイカレント・コンサルティング
(ま)マツダ,丸紅,三重県庁,三井住友銀行*,三菱鉛筆,三菱UFJ銀行*,みずほ銀行,みずほフィナンシャルグループ,明治,森永乳業
(や)ヤマハ発動機
(ら)リプライス
(他)JXTGエネルギー,PwCあらた有限責任監査法人
- ■主な卒論テーマ(ゼミ生は全文の閲覧が可)
2024年3月卒(第9期生)
- ジョイフル―コロナ禍で落ち込んだ業績の回復が遅れたのはなぜか―
- 女性取締役―女性取締役は企業パフォーマンスに本当に影響を与えるのか―
2023年3月卒(第8期生)
- 多角化戦略―多角化が企業の安定性に及ぼす影響とその種類―
- 株主集中度と株主総会活性化―株主多様化の今企業が取るべき姿勢―
- 生産拠点の海外展開―海外現地生産の推進は本当に必要な戦略なのか―
- ケーズホールディングス―「がんばらない経営」は収益性に貢献しているか―
2022年3月卒(第7期生)- 飲食業界―コロナ禍の業績予想開示と実際の業績および株価変動との関係性―
- 映画業界―興行収入の決定要因は面白さか話題性か―
- ダイエットと口コミ―口コミサイトの評価は実際の効果を示せているのか―
- コンサルティング業界―景気とコンサル会社の業績の間に相関やタイムラグはあるのか―
2021年3月卒(第6期生)- ふるさと納税の有効性―地方自治体の財政格差是正の観点から―
- ファブレス型経営―「製造しない」のは正解か―
- ゲーム業界−ゲームプレイ動画は敵か味方か?−
2020年3月卒(第5期生)- 企業年金―確定拠出年金の導入と業績―
2019年3月卒(第4期生)- 三洋電機はどこで道を誤ったのか?―選択と集中の重要性
2017年3月卒(第2期生)- フィリップモリスジャパン―マールボロは誰が吸う?―
- 広告業界―クリエイターはどのようにして生まれるのか―
- 商船三井―海運バブルの波で分かれた明暗―
- P&G―衣料用液体洗剤市場におけるトップシェア獲得の要因―
- ヤマハ発動機―二輪車部品からみる製品戦略―
- 大手私鉄における多角化と収益性―多角化はどうあるべきか―
2016年3月卒(第1期生)- デンソー―脱トヨタ戦略、恐れるトヨタ―
- 安川電機―ウサギとカメ、カメは勝者か―
- 任天堂―高営業利益率はどのようにして失われてしまったのか―
- キリンビール―プレミアムビールに参入しないのはなぜか―
- 富士フイルムHD―関連多角化による企業体質の変化―