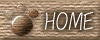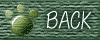エッセイ:三十路前の放浪記(2)
初めての職安
社会と繋がりを失くした私の不安は、次第にエスカレートしていった。
食事が喉を通らず、みるみる体重が減った。
もし、このまま大学院に入れなかったら…
もし、このまま仕事に就けなかったら…
もし、このまま大病に襲われたら…
もし、このまま死んでしまったら…
もし、このまま…
もし…
要らぬ押し問答ばかりを繰り返していた。◆
そうこうしているうちに、職業安定所(職安)に行く最初の日がきた。
失業保険をもらうため、すっかり疲れきった心と身体で私は向かう。
建物の中身は、どこか学習塾みたいだった。
周囲を見渡す。
皆、職がなく、職を探している人ばかりだ。
明らかに年配の人もいた。会社が潰れたんだろうか。それとも、会社を経営していて、借金難に陥ったんだろうか。
家族はいるんだろう。明日、飯を食う金に困る人もいるんだろう。
そんな集団のなかに、ぽつんと自分がいた。
講習を受け終わると、就職斡旋のための個人面接がある。
あらかじめ、どんな仕事を希望するかを記入する書類があって、私は「心理・教育職」と書いて提出した。事実そうだったし、そういう仕事には該当先がないのを知ってのことだ。
担当者は、中年の女性だった。
「こういう仕事、求人ないんですよね。」
「そうですか。」
「どうですか、以前の仕事の延長では…」
「それでは会社を辞めた意味がないですから。」
私は素直に言った。
「ええと、前の仕事は…あら、いい所に勤めてたのにね…ずっと機械相手で嫌になっちゃった?」
「朝から、晩までですから。」
担当者は、私をちらりと見て言った。
「そう、人間相手の仕事がしちゃくなっちゃった?」
−ああ、わかってくれる人もいるのだ。
当時の私は、この何気ない台詞にどれだけ救われたことだろうか。
この担当者は、疲れた私の顔を見て、わざと言ってくれたのかもしれない。
今やそれを知る由もないが、私はこの担当者に感謝する気持ちでいっぱいだ。
面接が終わり、折角なので、求人票のファイルをぱらぱらとめくってみた。
不景気とはいえ、以前の仕事の延長なら、まだまだ多くの求人があった。
−男ひとり生きていくことくらい、何とでもなるんだな。
帰り道の足取りは軽かった。前回へ戻る/続きを読む