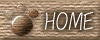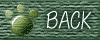エッセイ:三十路前の放浪記(5)
後悔
緊張の糸が切れたとはこのことをいうのか。
すっかり感情がなくなっていた。一歩も動けない。
冬の入試が迫っていた。走れば、まだ間に合う。
しかし、もはやそれに立ち向かう気力は、完全に失われていた。
たかが大学院の試験、と笑うかもしれない。
しかし私にとっては、誇張でなく生命を賭けた戦いに近かった。
このために生き、このために死ぬ。
それを私は求めていた。生きるための大学院であり、生きるための学問であった。
−徒労ではなかったのか。
大きな疑問が頭をもたげてきた。所詮、自分は何者にもなれないのではないか。
結局、生きていくことも、死んでいくこともできないのではないか。
何のために努力してきたのだろう。
会社も捨て、背水の陣で努力してきた。
それは一体、何のためだったのだろう。
そして私は、これから何を支えに生きていけばよいのだろう。
◆
太陽のない部屋。
転がったままのコーヒーカップ。
こころがきしむ日々。
生への問いと諦めが、自分を取り巻いた。
−もう、私はだめかもしれない。
そして私の思考は、あるひとつの問いへと向かっていく。
−何のために、私は生きるのか。
−何のために、私は死ねるのか。
光のこない部屋で、
ただ、そのことだけを考えていた。
何日も。
そして、何ヶ月も。
長い冬だった。前回へ戻る/続きを読む